【征幸治 第三話|やさしさを壊した日】
あの裏山の出来事から、
「人とは、違うふうに世界を感じてしまう」って自覚が生まれた。
けれど、幼い俺にはそれを言葉にする手段なんてなかったし、
周りの大人たちは、そんな違和感に気づく余裕もなかった。
当時、俺は保育園に通っていた。
身体が大きくて、目立つ存在だったけど、
実際の中身はガラス細工のように脆かった。
家でも外でも怒鳴られ、バカにされることが当たり前で、
「自分の感情を守る」という発想すらなかった。
そんな俺にも、心がほどける時間があった。
それが──マキちゃんとのおままごとだった。
マキちゃんは二つ年下で、一緒にスクールバスで通っていた女の子。
ある日、遊んでいた時に、マキちゃんが俺に“香水”をかけてくれた。
子ども用の、小さなボトル。
だけどその香りは、「人にやさしくされた」って感覚そのものだった。
「ええ匂い……」
小さくそうつぶやいたとき、胸の奥に、初めてほんのり“光”みたいなものが灯った気がした。
でも、それは一瞬で消された。
家に帰ると、祖母の低い声が響いた。
「男のくせに、気持ち悪いわ…何してんの、アンタ」
そのあとの言葉はもう覚えていない。
ただ、目の前が真っ白になって、
“あの匂いを落とすためだけの風呂場”に連れていかれたことだけが残っている。
嬉しかった記憶が、汚された。
心の奥に差し込んだ光が、「おぞましいもの」としてかき消された。
「俺、何か悪いことしたん?」
何度問いかけても、答えはなかった。
──それから数日後。
バスを降りたあと、大人の目が届かない一瞬があった。
俺は、その“スキマ”で、取り返しのつかないことをした。
マキちゃんの顔に、爪を立ててしまった。
彼女は一瞬、何が起きたのか分からないという顔をして、
次の瞬間には「信じていた人に裏切られた」ような目で泣きながら走っていった。
その表情を、俺は一生忘れない。
怒っていたんじゃない。
悲しんでいたんだ。
「なんで……?」
その無言の問いに、俺は何も答えられなかった。
そのくせ、「俺が壊した」という感覚だけが、胸の奥に深く深く沈んでいった。
たぶん俺は、“大人たちに否定されたもの”を、自分の手で壊すことで、
その痛みから逃げようとしたんだと思う。
「男が香水なんて気持ち悪い」
「年下の子と遊ぶなんておかしい」
そうやって大人が“汚い”と決めつけたものを、
俺はなぞるように、自分で壊した。
それが正しいとも思ってない。
でも当時の俺は、そうやってしか生きられなかった。
──後日、クレームの電話が入った。
母に怒鳴られた。
でも俺は、心の中で叫んでいた。
「これ……お母さんがいつもオレにしてることやろ?」
子どもながらに、本気で分からなかった。
“怒る”という感情の扱い方を知らなかった。
“優しさ”をもらった記憶を、守る術を知らなかった。
だから、俺はコピーした。
家庭の中で受けた“怒りの使い方”を、そのまま。
──そして、マキちゃんは保育園を辞め、引っ越した。
「ああ、避けられたんだな」
当然だった。
わかってる。俺が悪い。
でも、それでも……その拒絶は、俺にとって“永遠の断絶”だった。
「優しさ」に触れたはずだったのに、
俺はそれを、自分の手で壊してしまった。
しかもそれは、人生で初めて“あたたかい何か”をくれた存在だったのに。
──今でも思う。
「あの時のオレに、何て言ってやればよかったんだろう?」
「間違ってない」とも、「全部悪い」とも言えない。
ただひとつ、はっきり言えるのは、
「自分の痛みを、人に渡しちゃいけない」
ということ。
これが、俺の“やさしさの原点”だ。
それは最初からあったものじゃない。
壊したあとの、真っ白な場所からようやく探し始めたものなんだ。
【あとがき】
今でも時々思う。
あの香水の匂いが残っていたら、
もう少し違う自分になれていたのかもしれない。
でも、現実はそうじゃなかった。
だからこそ、今こうして書いている。
これは、過去を正当化するためじゃなく、
“やさしさを学び直す”ための物語なんだ。


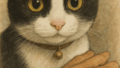
コメント