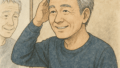笑わない母と、暗黒の土曜日
保育園のある月〜金は天国だった。おばあちゃんが迎えに来てくれ、図書館の移動バスで絵本を借りるのが日課だった。
でも土曜日は違った。
母が家にいた。6チャンネルの「夫婦でドンピシャ」を見て、暗い部屋でこっちを見ない。
僕が帰ってきても反応はない。
その背中には、機嫌の悪さがにじみ出ていた。
怒鳴り声と、お仕置きの暗室
母は、僕に八つ当たりした。理不尽なことで怒鳴り、叩いた。
鼻の下がかゆくて掻いていたら、「鼻くそをほじってる」と決めつけられ、手を見せた僕に「言い訳すんな」と叩いた。
怒られる理由がわからない。
ただ、否定される。その繰り返しだった。
そして、母は“真っ暗な部屋に閉じ込める”というお仕置きを繰り返した。
幼い僕にとって、これは「心を殺す刑罰」だった。
僕は感覚が人より敏感だった。
闇の中の空気、重さ、音。
すべてが、怖かった。
天国のような日曜日、そして──
日曜になると父が帰ってきた。
彼は模型を作ってくれ、優しかった。
怒らない。話を聞いてくれる。
でも後に知る。彼こそが、真の地獄だったことを。
麻疹に倒れた4歳の冬
4歳の冬、クリスマス前に僕は高熱で倒れた。
意識が朦朧とする中で、“この家はおかしい”と、心の奥がささやいた。
そして──
あの夜、僕は“何か”を見た。
次回予告
次回:「熱に浮かされた夜に、僕が見たもの」
この“はしかの夜”に現れた存在について、そして“覚醒”の最初の記憶を描きます。
あとがき
この物語は「誕生前夜」と題した、僕の原体験の記録です。
あの頃の僕と同じように、「誰にも言えない違和感」を抱えていた人に、届けば嬉しい。